もしAIがなかったら?――大学生の一日で実感した“AI前夜”と今の違い
はじめに:「もしもAIがなかったら?」を想像してみる
日々、レポートから就活、情報収集や趣味の管理まで、気づけばAIツールに頼ることが当たり前になっています。
でも、ふと「もし明日からAIが一切使えなかったら…」と考えてみたことはありませんか?
今回は、あえて“AI断ち”で一日過ごしてみた体験をレポートしつつ、親世代や友人にも「昔ってどうしてた?」と聞いてみました。
いつも通りの“AI活用生活”との違いや気づき。
そして今後のAIとの付き合い方についても、率直に考えてみます。
”もしもAIがなかったら?”を徹底的に深掘りしていきましょう。
- AIなしで過ごす大学生のリアルな一日体験
- 親世代・友人が語る“AI前夜”の勉強や生活
- AI導入で変わった日常と、そのメリット・デメリット
- これからのAI活用と“依存”の境界線についての考察
“AI無し”で過ごす1日――実体験レポ
普段、何気なく使っているChatGPTやAIスケジューラーを全カット。
まずレポート課題は、Google検索と参考書だけで取り組むことに。
情報収集は予想以上に時間がかかり、「どれが信頼できるか?」を一つ一つ確かめる作業も新鮮でした。
メールやLINEの返信もAI自動返信はナシ。
ちょっとした日本語表現や英作文も自分で考えると、意外と脳がフル稼働…。
アルバイト探しも求人サイトの「おすすめAI」は見ないルールで、手作業で条件を比べることに。
一番つらかったのは、時間管理。
いつもAIにリマインドを任せていたので、うっかり提出締切を忘れそうになった瞬間、少し冷や汗…。
親世代・友達に“昔どうしてた?”インタビュー
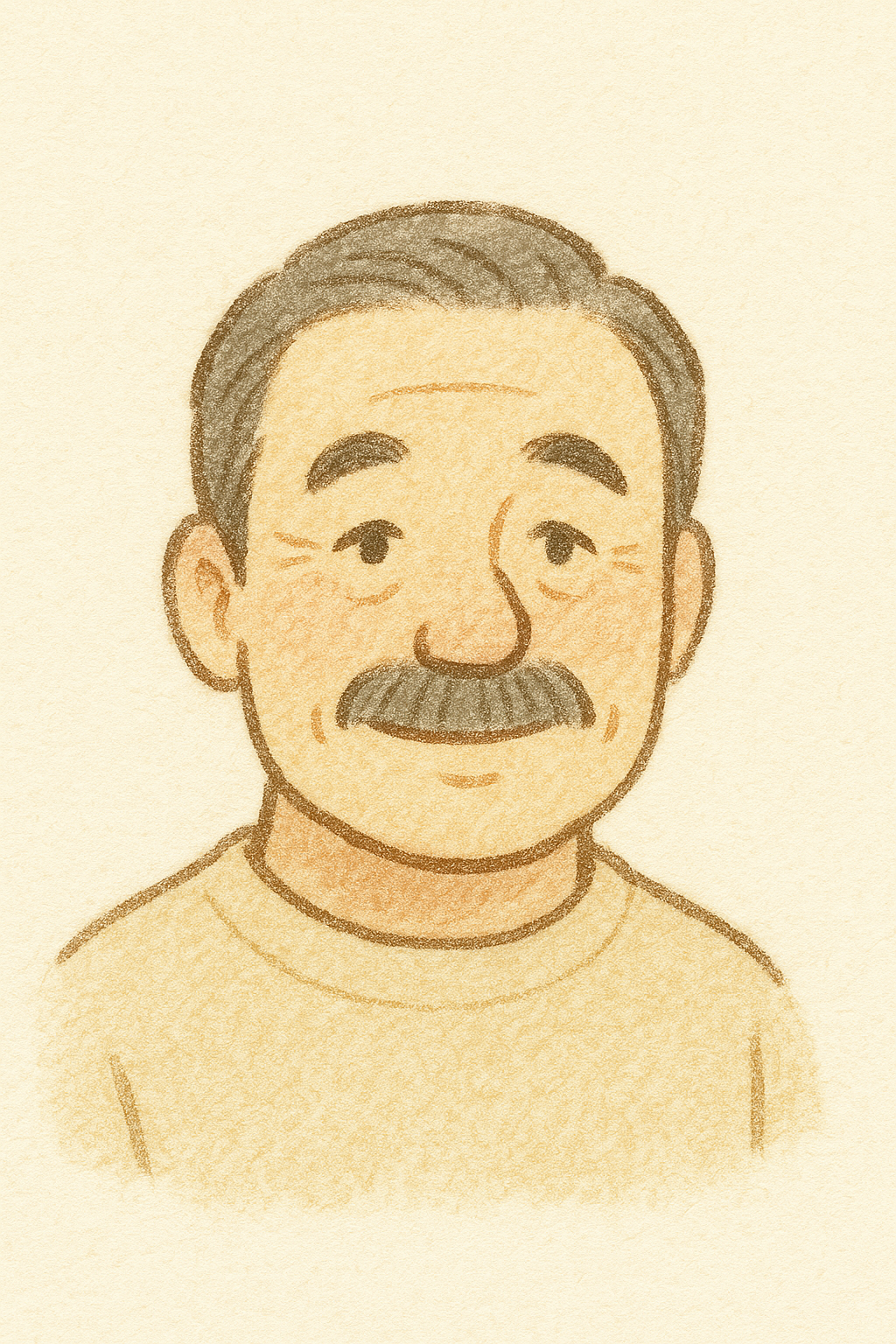
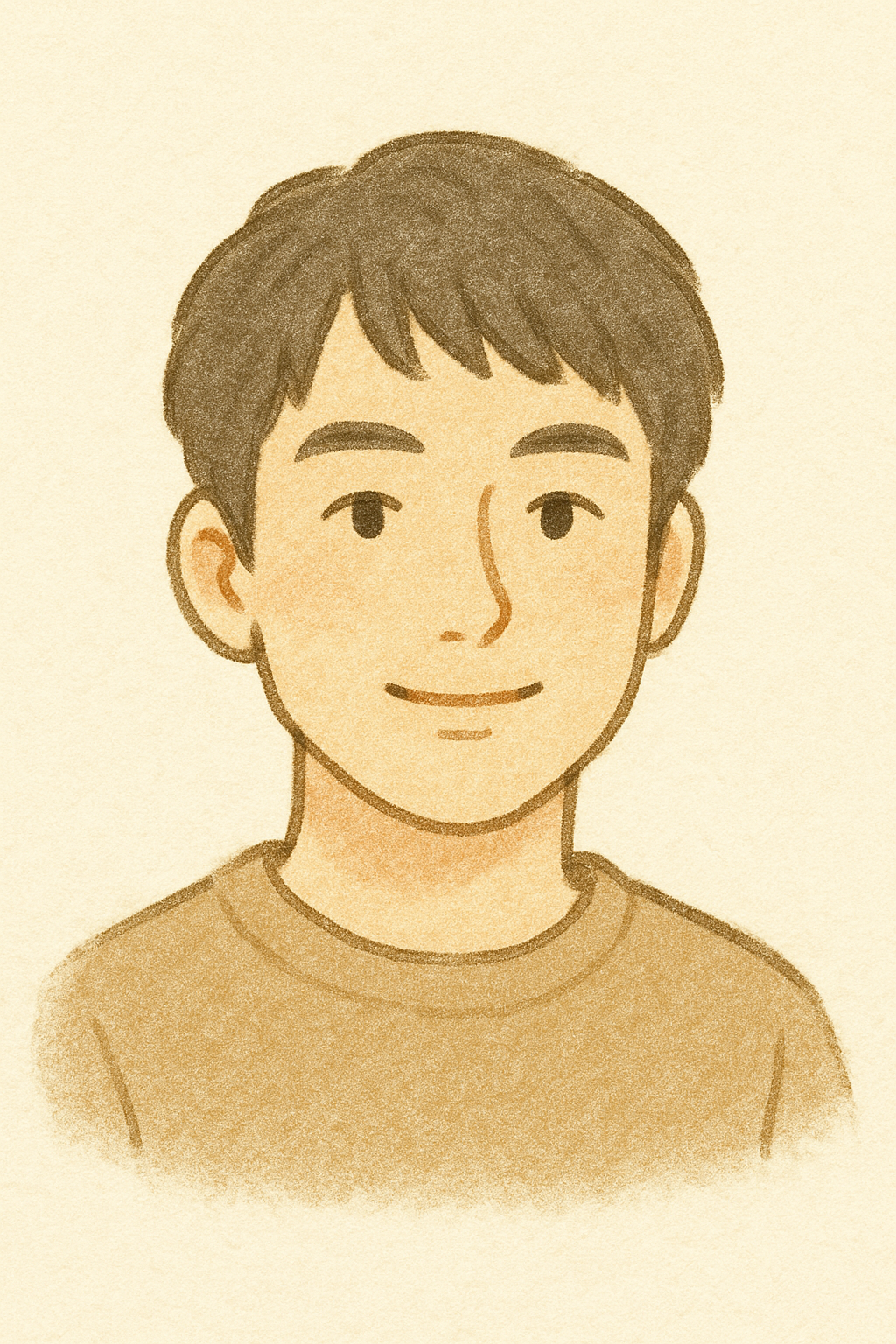
「今よりも時間はかかったけど、一度調べたことは絶対に忘れなかった」「分からないことを周りに聞く力が身についた」と、
懐かしさ半分、少し誇らしげな表情が印象的でした。
AI導入で変わったこと――自分と周囲の実感
AIを活用するようになってから、時短効果と情報の幅広さは明らかに向上。
「とりあえずAIに質問してみる」「複雑なスケジュールもサクッと整理できる」のは、もはや生活インフラレベル。
一方で、考える前に“AIに丸投げ”しそうになる瞬間も多く、「自分の頭で考えるクセ」が減っていないか、ふと不安になることも…。
“AI無し”で感じたメリット・デメリット
・深く調べるクセがつく
・集中力が続きやすい
・人との会話や助け合いの機会が増える
・とにかく非効率、疲れる
・情報の正確さを自力で確かめる手間
・ちょっと孤独感が増す
これからのAIとの付き合い方
「AIは便利だけど、使いすぎには要注意。」
AIを使うことで見えなくなっていた部分(調べる力・考える力・周囲とのコミュニケーション)が、逆に浮き彫りになりました。
今後は「どこまでAIに任せて、どこから自分で頑張るか」を意識的に線引きしようと思います。
たまには“AI断ち”チャレンジをして、自分の「地力」を点検してみるのもアリかもですね――。
まとめ|AIがなかったら?
「AIに頼らず1日過ごす」は想像以上に大変。でも、その不便さが“考える力”や“人とのつながり”を思い出させてくれました。
読者の皆さんは、もし明日からAIが使えなくなったらどうしますか?
※AI依存やITリテラシーで悩んだ場合は、警察庁サイバー犯罪対策ページや 内閣府こども家庭庁の相談窓口もご利用ください。
この記事を書いた人

AI活用アドバイザー/青山学院大学 経営学部
「AI時代の“本当に役立つ”一次情報を、現場目線で。
公式発表・実体験・専門家インタビューをもとに、
信頼性のある最新AI情報・ニュースのみを厳選して取り上げます。
誤情報・煽りや偏見を排し、
信頼できるAI活用ノウハウと
社会課題の“リアルな今”を発信しています。
・すべての記事は公式リリースや公的情報を確認のうえ執筆
・内容に誤りや古い情報があれば即訂正します。
「AI×社会」の最前線を、ユーザーの実感とともに届ける“みんなのAIメディア”をめざしています。

